【雑話】 キャピラリー電気泳動序論
4.ブラックボックス化
ゲル電気泳動は、生物化学と分子生物学の分野で実に様々な思いつき・工夫を産み出して、多彩な発展を遂げてきました。そこでは、いわゆる分析化学者の寄与は少なかったようです。それは、ゲル電気泳動が、実験をする人の身近なものとして存在したことに負うところが大でありました。キャピラリー電気泳動も、最初のうちは手作りの実に単純な装置から始まったのですが、自動化への適合性と必要性から、極めて急速に自動化、そして高級化が進行しました。そこでは、多くの分析化学者からの新規な方法の提案がありました。
しかし、ゲル電気泳動の場合のような、草の根からの提案といった方法論の展開は、ゲル電気泳動の場合と比較しますと、遙かに少ないままに推移してきたように感じられます。これは、キャピラリー電気泳動にとって不幸なことであると思います。生化学・分子生物学へのキャピラリー電気泳動の展開は決して順調とは云えません。ゲル電気泳動においては存在し、キャピラリー電気泳動に欠けているのは何でしょうか。それは、“身近さ”であると思います。
キャピラリー中の液体の挙動への関心は、次の記述から明らかなように、近代科学の端緒の一つであったようです:「17世紀になると分子間力の最初の科学的吟味が始まる.Newtonは分子間力が物体の物理的性質とどのように関係づけられるかを考察し、後年18世紀の多数の研究者はガラス管中の液体の毛管現象の研究を始めた。1808年にClairauntは液体とガラス分子間の引力がもし液体分子間の引力と異なっていれば毛管現象が説明できることを示唆した。また、液柱が上昇する高さは毛管の壁の厚さには無関係であることに気づき、これらの力のおよぶ範囲は非常に小さいという結論に達した。」(J.N.イスラエルアチヴィリ(Israelachvili)著・近藤保/大島広行訳、「分子間力と表面力(原著名:Intermolecular and Surface Forces: With applications to Colloidal and Biological Systems)」、マクロウヒル、1991)。私たちがキャピラリー電気泳動に接する際に、それを完成された分析手段としてしか、受け取っていないのではないでしょうか。キャピラリー電気泳動を、もっと身近なものとして、そこに出没する現象を、もっと好奇の目で眺めて、自らサイエンスするという姿勢が必要と考えられます。
最近、次の章で述べますように、キャピラリー電気泳動を、シリコンあるいはプラスチックスの小さな基盤に形成した毛細管中で行おうとする試みが盛んです。それらは、チップ電気泳動と呼ばれています。そこでは、使用者側から見るならば、ますますブラックボックス化が進行するでしょう。“身近さ”の取り戻し、あるいは維持は、容易なことではありません。
関連製品
| キャピラリ電気泳動システム Agilent 7100 |

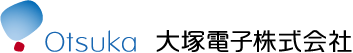
 Close
Close


