【雑話】 キャピラリー電気泳動序論
1.はじめに
“電気泳動”は伝導性の液体、したがって普通は水溶液、の中に存在するイオンが、電場を掛けられた場合に移動する現象です。それは、水溶液中の“電気伝導”と同じではないかと云われそうです。たしかに、電気泳動は電気伝導の一種であると云えるかも知れません。今日、電気泳動という概念を特徴づけているのは、そこで何かを行いたいという意志が働いていることではないでしょうか。つまり、イオンの移動を定量的に測定しよう、あるいは移動速度の違いによって、それらを分離・分析しようとしているのです。
ところで、私たちは“対流圏”に住んでいて、常に対流という現象から極めて大きな恩恵を受けています。しかし、“電気伝導”ではなく“電気泳動”を実現しようとすると、対流ほど面倒なものはありません。
昔から、気体にせよ液体にせよ、厳密に対流なしの条件下で物性の測定を行うことは、非常に困難なことでした。その典型例の一つが“拡散定数”の決定でありました。厳密な恒温に保ったうえで、内部の状況を精密に測定する必要があったのです。この際に、二つのアプローチが行われております。一つは、溶液の方が密度が高いから下におき、密度が低い溶媒の方を上におき、両者の間に形成させた鋭い境界が、時間の経過とともに“ぼやけてゆく”のを観察する方式(I)でありました。もう一つは、キャピラリーを用いるものでした。“キャピラリー”という用語をつかいましたが、以前は“毛細管”あるいは“毛管”と呼ぶことが多かったようです。ここでは“キャピラリー”を用います。そこでは、二つの方式が試みられました。一つは多孔性の隔壁を用いる方式(IIa)であり、他は円筒状のキャピラリーを使用する方式(IIb)でありました。
方式Iでは対流の発生を、正直に真正面から防止しようとしたのに対して、方式IIではキャピラリーを用いることにより、簡便な対応で対流の発生を回避あるいは抑制したと云えるでしょう。方式 IIaでは複雑に入り組んだキャピラリーが、方式IIbでは単純に真っ直ぐなキャピラリーが用いられました。
電気泳動の世界でも、19世紀初頭に始まって、20世紀の半ば過ぎ頃までは、方式Iに近いものが、幅をきかせていました。これを“自由境界電気泳動”と呼んでいましたが、今では博物館に行かないと装置を見ることはできません。その後、IIaの全盛時代を迎えて、今日にいたっています。これには、色々の方式が考えられましたが、今日でも元気なのは、“ゲル電気泳動”がそれです。IIbは、ようやく20年ほど前から実用性が評価されるようになり、また周辺環境もようやく整って、発展し始めました。それが、“キャピラリー電気泳動”です。ゲル電気泳動も、一種のキャピラリー電気泳動ではあるのですが、この名称は円筒型キャピラリーと、その系統を引く真っ直ぐな単純明解なキャピラリーを用いる方式の電気泳動に限って使われています。
関連製品
| キャピラリ電気泳動システム Agilent 7100 |

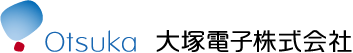
 Close
Close


