専門用語集 あ行
専門用語集 か行
- 拡散係数
- 粒子のブラウン運動による拡散速度を表し、並進拡散係数とも呼ばれる。 粒子径が小さいほどブラウンは速く、大きいほどゆっくりになる。よって小さな粒子ほど拡散係数は大きくなる。 拡散係数は、動的光散乱法より求められ、拡散係数から粒子径が演算される。
- 慣性半径
-
静的光散乱測定において得られる散乱体の大きさを示す量(Rg)であり、二乗平均回転半径の平方根(<S2>1/2)や単に回転半径とも呼ばれる。
主に高分子の大きさや広がりを示す。慣性半径は、高分子にレーザーを照射し異なる検出角度で得られる散乱光強度を解析することで求められる。
【関連機種】DLS-8000
- 輝度
- 面光源をとある観測点で見たときの光の明るさを示す。単位は、カンデラ毎平方メートル(cd/m2)。テレビなどの面光源の明るさを示す指標として用いられる。
- キャピラリー電気泳動
-
溶液サンプルを内径100um以下のキャピラリー管の中で電気泳動させ、測定成分の電荷やストークス半径による電気泳動移動度の違いから成分を分離、定性、定量する方法。
陽イオンや陰イオン、金属イオン、有機酸などを分析することができる。夾雑成分の影響を受けにくく、簡便に多成分を分析できる手法。
【関連機種】Agilent7100
- 吸光度
-
物質に光を照射し、どれだけ光吸収をするかを示す指標。吸光度(A)は、主に透過率測定の対数より求められ、透過率が10%(0.1)では、A=1、透過率0.1%(0.001)では、A=3と吸光度が値が大きいほど光透過性が低い。
【関連機種】MCPD
- 蛍光スペクトル
-
蛍光体にとある指定した波長の励起光を照射し、その時に得られる各波長における蛍光の分光スペクトルを示す。
どの波長で蛍光強度が最大になるかなどを調べることができる。
- 検量線
-
標準物質とそれに対応する測定データとの関係を示したグラフ。
あらかじめ濃度の既知のサンプルを複数濃度測定することで検量線を作成し、未知濃度成分の定量を行うことができる。
クロマトグラフィーなどの分離分析などの定量測定に活用される。
【関連機種】Agilent7100
- 光学定数
- 物質の屈折率n、消衰係数kを合わせたもの。光干渉法による膜厚解析では、対象の膜のn,kを必要とする。 顕微分光膜厚計やエリプソメータを用いることでn,kの解析を行うことができる。
- 光学膜厚
- 光干渉法による膜厚計によって得られる厚み(nd)のこと。主に屈折率未知の膜や多層膜の解析に用いられる。 光学膜厚=屈折率(n)×膜厚(d)として表される。測定対象膜の屈折率を割り算をすることで対象の物理厚みを得ることができる。
- 光子相関法
- 動的光散乱の粒子径計測において主に用いられる手法の一つ。 ホトンカウンティング方式とも呼ばれ、溶液中の粒子の散乱光を光電子増倍管などの光変換検出器で検出し、非常に短い時間間隔内での散乱強度の時間変化を演算することで、ブラウン運動の速さおよび粒子径を測定する方法。
専門用語集 さ行
- 散乱ベクトル
-
物質に光を照射し、散乱する際の光の方向と速度の変化を示す。
粒子径測定などの光散乱測定における重要なパラメータとして用いられ、光の波長、散乱角度、媒質の屈折率により演算される。
- 色度
- 刺激値直読測色と分光測色がある。光源や物体の色を定量的に表した量で、色度図上の座標の数値で表される。色度図には、XYZ表色系やL*u*v*表色系などがある。
- 自己相関関数
- 動的光散乱を用いた粒子径測定に用いられる減衰曲線のこと。
粒子から散乱されたとある基準時間の散乱光強度と任意時間での散乱光強度の関係を示したもの。
自己相関関数の減衰する速さや傾きを解析することで、粒子径および粒子径分布が解析できる。
- 小角光散乱法
-
高分子溶液およびフィルムにレーザー光を照射し、小角度の散乱パターンおよび散乱強度を解析することで、内部構造の大きさや構造を推定する方法。
平行ニコル(VV)散乱や直行ニコル(HV)散乱を用いることで、ポリマーブレンドの相関長や結晶性高分子の球晶径を測定する。【関連機種】PP-1000
- 周波数解析
-
光干渉法による膜厚計で取得した、反射スペクトルの解析方法の一つ。
周期的に現れた反射率のピークとバレイを高速フーリエ変換(FFT)を用いて周波数解析することによって膜厚を演算する方法。
ピークとバレイが複数以上得られる数μm以上の薄膜やフィルム、Siウェーハなどの基材の厚み解析に適用される。
- 照度
-
光源に照らされた面の単位面積当たりの光束のこと。
単位は、ルクス(lx)。任意の場所における明るさを表す指標として用いられる。
照度は、光源と観測点の距離によって変化するため、部屋やデスクなどの明るさの定量化に用いられる。
- 静的光散乱法
-
高分子の絶対分子量を測定する方法。
高分子溶液にレーザー光を照射し、濃度や検出角度における散乱光強度を解析することで、重量平均分子量(Mw)や慣性半径(Rg)、第二ビリアル係数(A2)測定する方法。
標準試料を必要とせず、絶対分子量が得られることが特徴。
- ゼータ電位
-
粒子表面の荷電状態を反映する値。
溶液中に懸濁した粒子と周辺のイオンによって形成される電気二重層の外側のすべり面での電気的なポテンシャルを示す。粒子分散液の分散性、分散安定性を評価する指標として用いられる。【関連機種】ELSZ
- セルギャップ
-
液晶ディスプレイの液晶層の厚みのこと。
【関連機種】RETS
- 全光束
-
光源があらゆる方向に放射する光束の総和を示す。
単位は、ルーメン(lm)で表される。
全光束は、人間の感度に基づいた電球などの照明などの明るさを表す指標として用いられる。
- 全放射束
-
光源からあらゆる方向に放射される単位時間当たりのエネルギーの総和を示す。単位はワット(W)で表される。
電球などの照明の明るさを示す指標として用いられる。
- 相関長
-
複数の高分子を混合した際などに生じる相分離によって形成された相構造の構造周期の大きさの尺度を示したもの。
ポリマーブレンドなどの海島構造の構造周期や相分離過程の解析に用いられる。【関連機種】PP-1000
専門用語集 た行
- 第二ビリアル係数
-
第二ビリアル係数(A2)は、溶液中での分子間の引力と斥力の度合い示し、溶媒の分子に対する親和性や結晶化の目安になる。
A2が正の場合、親和性が高い良溶媒となり、斥力が強く、安定に存在しやすい。
A2が負の場合、親和性は低い貧溶媒で、分子間の引力が強いため、凝集が起こりやすくなります。
A2=0の場合、シータ溶媒となり、結晶化が起こりやすくなる。
静的光散乱法において濃度による散乱光強度を解析することで得られる。
- 多分散指数
-
多分散指数(polydispersity index)は、粒子径分布の広がりを表す指標。
大きな値であるほど多分布となり、分散性の指標として用いられる。
典型的な単分散の粒子分散液では、PIは、0.1以下と小さな値を示す。
動的光散乱法による粒子径測定において得られる。
- 電気泳動移動度
-
溶液中の粒子が持つ電荷に応じた電気泳動のし易さを示したもの。
電気泳動移(易)動度は、電気泳動光散乱法より求められ、その値から粒子や平板のゼータ電位が算出される。【関連機種】ELSZ
- 電気泳動光散乱法
-
粒子のゼータ電位を測定する方法。
溶液中の粒子に電場を与え、粒子が持つ表面電荷に応じた電気泳動移動度をレーザー光を用いて計測し、粒子や平板のゼータ電位を算出される。
コロイド分散液の分散性を評価する際に用いられる。
JIS Z8836:2017やISO13099-2:2012など工業規格として定められる計測手法。【関連機種】ELSZ
- 透過率
-
物質に光を照射した際の入射光と透過光の比率を示したもの。
拡散透過と直線透過に分類する事ができる。
入射光をすべて透過する場合には、透過率は100%となる。
透明体ほど透過率は高く、光吸収や光散乱が生じるほど低下する。
- 動的光散乱法
-
粒子分散液にレーザー光を照射し、粒子のブラウン運動による散乱光の揺らぎを解析することで粒子径および粒子径分布を測定する方法のこと。
主にnm~µmのコロイド粒子の粒子径を高精度の計測することができる。
JIS Z8828:2019やISO 22412:2017など工業規格として定められる計測手法。
- 等電点
-
粒子のゼータ電位がゼロとなるpHのこと。
等電点では、粒子の静電斥力がないことから凝集しやすくなる。
粒子分散液の分散性を検討する際などに測定される。
pH滴定装置を併用してゼータ電位測定を行うことで、等電点を得ることができる。
専門用語集 は行
- 配光
-
光源からの空間方向へどの方向(角度)にどれくらいの強さで発しているのかを示すもの。
LED光源などの光の指向性の評価に用いられる。
- 反射率
-
物質に光を照射した際の入射光と反射光の比率を示したもの。
拡散反射と正反射に分類する事ができる。入射光をすべて反射する場合には反射率は100%となる。
反射率には、相対反射率と絶対反射率がある。
- 光干渉法
-
薄膜に光を照射し、反射率を用いて膜厚を求める方法。
膜の表面および裏面で生じる反射光は、光路差(厚み)による位相のずれによって光干渉現象が生じる。
この干渉光の分光反射率を周期性解析やフィッティング解析を行うことで、膜厚を測定する。
非接触、非破壊でnm~µmの厚み測定ができる。
- フィッティング解析
-
光干渉法による膜厚計で取得した、反射スペクトルの解析方法の一つ。
測定によって実測された反射率と理論的な反射率をフィッティング解析することによって、膜厚を演算する方法。
数µm以下の薄膜の解析に適用される。
膜厚解析とともに光学定数(n,k)も解析することができる。
- プレチルト角
-
液晶層の傾き角のこと
【関連機種】RETS
- 分光器
-
光を波長ごとに分光した光強度を測定する装置を分光器という。
サンプルの透過率や反射率、蛍光などのスペクトルを測定する検出器として用いられる。
モノクロメータは、分光素子を駆動させながら連続的にスペクトルを獲得する。
ポリクロメータは、分光した光を一括で取得し、高速なスペクトル測定に適している。【関連機種】MCPD
- 分光測定
-
サンプルに光を照射し、透過、吸収、反射、蛍光などの光学的な性質や化学的な性質や成分の量など調べることができる。
光源と分光器を測定対象および測定項目合わせて適切に配置し、透過率、吸光度、反射率、蛍光スペクトルなどを獲得できる。【関連機種】MCPD
- 分子量
-
分子量:Molecular Weight(MW)。高分子などの化学物質に含まれる原子量の総和。
静的光散乱測定のように標準サンプルを必要としない、絶対分子量とGPCのように標準サンプルを用いた相対分子量がある。
専門用語集 ま行
- マイクロレオロジー
-
溶液中の粘弾性測定を行う方法のひとつ。
動的光散乱法を用いて、溶液中に添加したプローブ粒子のブラウン運動を解析することで粘弾性が得られる。
水のような低粘弾性サンプルの高精度な粘弾性測定を可能とする。【関連機種】ELSZ
専門用語集 ら行
- リタデーション
-
複屈折物質に直線偏光を照射すると、屈折率の高い方向(遅相軸)と低い方向(進相軸)へ透過する光に位相差が生じる。物質に光を透過した時に生じる複屈折位相差をリタデーション(Δnd)と呼ぶ。
ディスプレイ用途など光学補償をする位相差フィルムの設計に用いられる。
- 粒子径分布
-
粒子分散液の中の粒子の粒子径を頻度分布として表したもの。
動的光散乱法では、散乱強度基準の粒子径分布が得られる。
粒子の分散、凝集状態の評価に用いられる。
- 量子効率
-
蛍光体へ光を照射し、励起光と蛍光の光量子数の比率より求められる。量子効率が高いほど入射光が多く蛍光に変換される。励起光量子数と発光光量数より得られる外部量子効率、吸収光量子数と発光光量子数と内部量子効率がある。蛍光体の蛍光特性を評価する際に用いられる。
【関連機種】QE
- 励起スペクトル
-
励起光の波長を変化させながらとある波長の蛍光強度のプロットしたもの。
蛍光体の光吸収する波長と相関し、励起波長を確認することができる。【関連機種】QE
- レイリー散乱
-
粒子に光を照射し、光の波長より十分小さい粒子から生じる散乱現象。
短い波長程散乱されやすく、昼間の空が青いことの要因としても知られる。
レイリー散乱によって得られる散乱光の強さは、波長の4乗に反比例し、粒子径の6乗に比例する特徴を持つ。
動的光散乱や静的光散乱を用いた粒子径、分子量測定は、レイリー散乱光を観測することで測定される。
- レーザードップラー法
-
電気泳動光散乱法を用いたゼータ電位測定の方法の一つ。
電気泳動する粒子にレーザー光を照射し、電気泳動速度を粒子からの散乱光のドップラーシフト現象を用いて計測する。
電気泳動しない散乱光との周波数の差を解析することで電気泳動移動度およびゼータ電位を測定する。
JIS Z8836:2017やISO 13099-2:2012などの工業規格として定められる計測手法。【関連機種】ELSZ
専門用語集 わ行
専門用語集 DEF
専門用語集 JKL
- JCSS
- Japan Calibration Service System:計量法校正事業者登録制度のこと。
日本の測定標準とキャリブレーションサービスの追跡可能性、信頼性、および精度を確保するための枠組みのこと。【関連機種】GP , JCSS校正サービス
専門用語集 PQR
専門用語集 STU
- TTV
-
Total Thickness Variationの略。
ウェーハの厚さの最大と最小の差を表す。
ウェーハの平坦度を示す指標として用いられる。【関連機種】SF-3

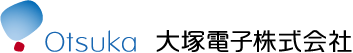
 Close
Close

